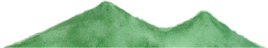真夏の照り付ける日差しのなか、半袖シャツの上からさらに長袖を2枚重ね着し、軍手とゴム手袋を2重にはめて、口元まで覆われる目深な帽子をかぶる。足元はチノパンに長靴。これが私の漆掻きスタイルである。
「漆掻き」というのは木に傷をつけて樹液を採取する作業のことで、6月から10月までのシーズンの間、この服装でだいたい4日に一度のペースで作業に向かう。腰に付けた道具箱から鎌を取り出し、ごつごつとした硬い木の皮を剥ぎ、カンナと呼ばれる刃物で一筋ずつ傷を入れていく。みるみるうちに傷口から乳白色のとろりとした樹液が滲んでくる。これが漆。
それをできるだけ無駄のないように素早くヘラですくい取る。もたもたしているとどんどん出てくるので休んでいる暇はなく、作業が終わる頃にはいつも汗びっしょりになる。

傷を付けると乳白色の漆。硬化すると黒っぽく変化する
8月は漆掻き職人の間で「盛り(さかり)」と呼ばれ、木が元気になり、漆がたくさんとれる時期である。作業中は樹液が身体に着きやすいので、かぶれを防ぐために暑さを我慢して厚着をする。服のあちこちについた漆の黒いシミは、洗濯してもとれない。それほど強固な塗料なのだ。昔から接着剤として使われていたのも頷ける。
「植えないでほしい」という意見
「まけへんの?」
曽爾で地元の方と世間話をしていて漆のことに触れると、ほとんどの人からこう聞かれる。「まける」というのはこの地域の方言で、漆にかぶれるという意味らしい(関東出身の私にとって、この言い方が曽爾特有なのか、関西特有なのか、奈良県特有なのか、いまだに分からない)。
山を身近に生活している人の多くは、「漆」と聞くと、まず植物としての「ウルシ」を連想し、それによって「かぶれる危険な木である」という意識が強く根付いている。そういうイメージを持っている人にとって、進んで漆に近寄っていく行為は、なんとも信じられないようだ。私が「もう慣れましたよ」と笑って答えると、みんな不思議そうな表情を見せる。
「漆かぶれ」はアレルギーのようなもので、人によって性質の差が大きく、その症状が強く表れる人もいれば、皮膚に付着してもまったく異変が出ないという人もいる。私の場合は漆に初めて触った10年程前には、顔の輪郭が変わるくらい症状が出たけれど、少しずつ耐性がついているようで、今はそこまで深刻化することはない。
それでも漆掻きをしていると、膝や肘など思わぬところに樹液が付いていることがあり、しばらく赤く腫れているようなこともしばしば。一緒に漆掻きの作業をしている「漆ぬるべ会」の松本会長とメンバーの中村さんも、当初はかぶれがひどくて診療所に駆け込むこともあったが、今では「少しずつ耐性がついてきた」と笑う。

不安定な足場に気を付けながら漆を掻きとっていく
「家の近所に漆を植えるのはやめてほしい。」
ときどき、困った表情でこう漏らす住民さんもいる。曽爾村の有志グループ「漆ぬるべ会」が10年以上のあいだ漆の木の植栽や生育管理を続けていても、漆はかぶれるというマイナスイメージは簡単にはぬぐえない。地元の方の中には、「植えられては困る」という意見を持つ人もいるのだ。これまで、漆がこれほどに嫌悪される木であるということはあまり意識したことがなかった。
金や貝で緻密な装飾が施された朱や黒の漆器。素朴な塗りの民芸品らしい家具やうつわ。寺社建築の神聖な太い柱や、薄暗い空間にひっそりとたたずむ仏像。割れた陶磁器を漆で修理する「漆継ぎ」。
人によってさまざまだと思うが、いずれにしても漆は日本の文化を象徴する、誰にも好感を与えるイメージが一般的だと思っていた。ここ最近は国産漆が減少している問題がメディアでたびたび取り上げられるようになり、生産の関心をもつ人も増えたように思う。だから漆を植えることに対して否定的な意見が出ることに、最初は驚いた。
でもそれは、私が都市で生活しながら漆の文化的な側面や製品としての価値に注目していたからこその印象であって、山に生息する漆を見慣れている人にとっての「日常の中にある姿」とは全く異なるものだ。そう考えると、否定的な意見が出ることは当たり前なのだと思う。
漆に限らず、多くの素材は流通の過程でその姿を変化させながら私たちの手に届けられる。きっとあらゆる素材や食材において、同様のギャップは生まれるものなのだろう。
全国の産地とともに
昨年、曽爾村で採れた漆の量は682g。混ざっているごみを濾すと560gだった。
それをチューブ6本に詰めて保存しているが、漆の産地として有名な岩手県二戸市では、ブランドである「浄法寺漆」の1シーズンの生産量が約1040kg(平成29年)というから、比べものにならないほど僅かな量であることがお分かりいただけるはず。だけれど、この地域で採れる漆はここにしかない。
昨年はその二戸市で開かれた漆の品評会の中で、全国の産地が集まって採取した漆を展示する機会があり、曽爾村も参加させてもらうことができた。そこでは、曽爾村と同じように中小規模で生産に取り組んでいる人が全国各地から集まり、木の生育のことや漆掻きのことなど、各地の状況と想いを共有することができた。
地域は違っても、同じような悩みを抱えながら漆生産に関わるみなさんと交流できたことによって、全国規模で協力しながら共通の目標に向かっているのだという一体感が生まれたように感じる。

全国で採取された漆に混ざって曽爾村産の漆が展示された
私は曽爾村に来てから初めて漆掻きを経験し、それまで見たことのなかった荒々しく野生的な漆の一面と向き合うようになった。そして初めて、この素材が遥か昔から人々を魅了させ続けてきた所以を見ることができたと感じている。
木に傷をつけていると、その痛みを共有するような感覚が生まれることがある。
木は、動物のように動くことはないし、草花のように1シーズンで成長が感じられるものでもない。でもその分、内側から発される静かな気配があり、日々の気候や季節によって毎回表情が変わる。シーズン中に何度も同じ木と対峙して刃物を入れ続けるからこそ 感じ取れる変化だ。
おそらく各地の生産地でも、漆掻き職人がその土地の木と対話しながら漆を採取しているのだろう。

シーズンが終わると、その年に採取した木を伐採し、切り株から新たな芽を育てる
繋ぎ、続けていくことを目標に
漆をより多く生産するために、ただ大規模な植栽を行えば良いかというとそうではない。小さな規模でも健全な漆の森を長期的に管理していくことが重要で、漆の生産を続けるためにはその仕組みづくりから始めなければならない。曽爾村が今後どのようなかたちで活動を展開していくか、まだわからない。それでも、これまでの活動を繋いでいくこと、続けていくことが大切だと私は考えている。
嫌われたり、恐れられたりする反面、その美しく頑丈な塗料としての質を、遥か昔から保ち続けてきた漆の木。その魅惑的な素材が今後も守られ、私たちの生活の一部となって生き続けることを願っている。
Writer|執筆者


並木 美佳Namiki Mika
東京都生まれ。2017年より地域おこし協力隊として曽爾村に移り住み、漆の森づくりや採取、商品開発に取り組む。文や写真で村の暮らしを伝えながら、草木染めユニット「山杜色satoiro」としても活動中。