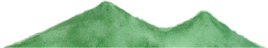高取町で栽培されはじめた薬草「大和当帰」

山城に続く古い町並みとひろがる田畑。奥大和の入り口に位置し、かつて「薬のまち」として栄えた町、高取町。昔ほどの賑やかさはなくなってしまったが、今も多くの製薬会社が商いを行っている。
高取町と薬の歴史は古く、飛鳥時代までさかのぼる。西暦612年、推古天皇が「薬狩り(薬用となる鳥や獣を捕る、あるいは草を摘む)」を行ったことを、歴史書『日本書紀』が伝えている。当時から、この地は豊かな自然に恵まれ、薬となる動植物が豊富な場所であったということだろう。

この地で、数年前から「大和当帰(やまととうき)」という薬草が栽培されはじめた。
「当帰」はセリ科の植物で、根は生薬として「当帰芍薬散・四物湯」などの漢方処方薬に配合されている。血行改善や鎮痛作用などの効能があるとされ、生理痛や冷えなど女性の健康を支えてきた代表的な生薬だ。
日本では北海道で栽培されている「北海当帰」、大和地方(奈良県・和歌山県)で栽培されている「大和当帰」が生産の大部分を占めており、なかでも「大和当帰」は香りが強く品質が良いとされてきた。

しかし昨今は、奈良県・和歌山県の両県境でわずかに栽培されているだけであったため、奈良県が「漢方のメッカ推進プロジェクト」を立ち上げ、県内各地で栽培拡大に向けて取り組みを進めている。
高取町では、農業生産法人「ポニーの里ファーム」が中心となり、大和当帰を栽培。ハーブソルトやドレッシングといった加工品もさまざまつくられており、「ポニーの里ファーム」で栽培された大和当帰葉を用いて商品化された「奈良高取の冷えない大和当帰茶」は無印良品でも販売されている。
そんな、大和当帰の生産から加工・販売までを行っている「ポニーの里ファーム」の統括マネージャー・保科政秀(ほしなまさひで)さんにお話を伺った。

保科政秀(ほしなまさひで)
京都府出身。大学院生時にフィールドワークを高取町で行い、まちづくりに携わる。民間企業に勤務の後、2013年から農業生産法人「ポニーの里ファーム」統括マネージャーとして、薬草の六次産業化や様々なイベントを実施する等、地域の農業発展に取り組んでいる。
ちょっと植えてみようかくらいの気持ちだった

「ポニーの里ファーム」は、障がい者のための「乗馬セラピー」を普及させる活動をおこなっていたNPO法人「ポニーの里をつくろう会」の農業部門として誕生した有限会社だ。
設立のきっかけは、ある親御さんから「子どもたちが学校を出た後の就職につながるようなことや、仕事の訓練になるようなことはできないか」という声があがったこと。障がいを持つ子どもたちの仕事づくりの一貫として、農業できちんと収益をあげ、福祉に関わる人たちの雇用を生むため、別会社として立ち上げられた。
当初は、「障がいがあっても育てやすい」という観点で作物を選び、青ネギと米を生産。初めから大和当帰を栽培していたわけではなかった。
保科さん 大和当帰は2011年ごろから始めました。奈良県の職員さんから苗を分けていただいて、和歌山県の富貴という大和当帰の産地へ見学に行って。ちょっと植えてみようかくらいの気持ちだったんです。でも、次の年に採れた大和当帰の根っこを生薬問屋さんに見ていただいたら、「すごく質が良いし土地にも合っているんじゃないか?」と言ってもらえて。じゃあ頑張って育ててみようかと(笑)。
県も町も本格的に取り組みをはじめるなど、タイミングにも恵まれた。県では「漢方のメッカ推進プロジェクト」が発足し、町はさまざまな研究機関を招き、種の蒔き方、苗の作り方、植え付け方などの栽培講習会を開いてくれた。
同時期に、今まで根っことともに「医薬品」とされてきた葉の部分が「非医扱い」に変わる。セロリのような強い香りのある葉は食品としての利用が可能となり、また6次産業認定※を受けたこともあって、「ポニーの里ファーム」は栽培した大和当帰葉を用いての加工品づくりや、イベントへの出店・販売など、薬草の6次産業農家として活動を広げることができたのである。
※農林漁業者自らが生産だけでなく加工・流通販売を一体的に行ったり、農林漁業者と商工業者が連携して事業を展開したりする取り組み
何のために、誰のために、儲けたいのか
そんな「ポニーの里ファーム」で、保科さんは主に商品開発や営業、イベント企画などを担当している。


商品づくりや農業体験のほか、まちづくり活動も積極的に実施。薬膳のお店や薬草を使って活動されている方々と一緒にワークショップを開催したり、ツアーを組んだり。町内のイベントはもちろん、県内外のイベントへの出店もかなりの数をこなしている。その甲斐もあって、メディアに取り上げられることも多くなり、商品も売れるようになってきた。しかし、「そこには難しさもある」と保科さんは話す。
保科さん 確かに物は売れるようになりました。でも当たり前のことなんですけど、動けば動くほど経費がかかってくるので、そこがやっぱり難しい。大量生産・大量消費しないとなかなか利益が上がってこないけれど、そうもしたくない。
「いい車に乗りたい!」とかいう欲求はなくはないけど(笑)、「めちゃめちゃ儲けたい」っていうのは正直あんまりなくて。それよりも「儲け続けること」が大事で。人をきちんと雇用できるとか、スタッフが働く環境をよくするために、お金が必要やなって思うんです。
お茶のブレンドも、袋詰めも箱詰めも、全部障がいをもつ子たちがやってくれています。彼ら・彼女らの仕事は、やっぱり物が売れないとつくれない。売る側の責任として、「もっと売らないといけないよね」って。その辺の想いは、スタッフはみんな持ってくれています。
農業をずっとやってきたわけでもないし、福祉をしたいからやっているわけでもない。けれど、これらの商品を売ることが、地域にとってとか、関わる人を幸せにすることだという共通の認識はある。だから、大変なこともみんなで共有してやれてるんかなと思います。
「キハダ」を用いた、新たな商品づくり
そして保科さんは今、新たな商品づくりにも奮闘している。それが「キハダ」を用いた商品だ。

保科さん 「地竜エキス」って書いているのはミミズなんですよ。解熱とか鎮痛とか痛みに効く。生薬って熊の肝を使っていたり、すごいんですよ。こっちはセンブリ、オウバクとか書いてますね。生薬になると名前が変わるものもあって、オウバクはキハダという木の皮からできていて、5mくらいの高さの木なんですけど、茶色い外皮を一枚めくると黄色い皮が出てくる。その黄色の皮を剥いで乾燥させたものです。

保科さん 生薬って苦味成分が良いといわれていて、キハダもすごく苦いんです。奈良では古くから胃腸薬として愛用されている「陀羅尼助」にも含まれているんですけど、陀羅尼助の苦さの正体はこのキハダ。農家さんたちは皮だけ乾燥させて出荷しはるんですけど、皮を取って残った芯材の部分は捨てられてしまっていて。それって勿体ないと思って、余った芯材の部分を木材加工して、磨いてコースターをつくってみたり、いろいろ試しています。
現在は耕作放棄されているものの、高取町にもキハダの畑があるという。
保科さん 山添村は70~80歳くらいのおじいちゃんたちがチェーンソーを持って作業してはるんです。20~30年くらい前に国産のキハダを植えましょうってブームがあったらしく、ちょうど収穫時期を迎えているので、山添村に行って木を切る手伝いとかして、お駄賃の代わりに木材を貰って試作しています。
「五條高等学校賀名生分校」の農業コースの高校生たちが今、キハダの苗を栽培しているんです。地道にキハダに対して取り組んでいる高校生がいることを、知ってもらえる機会もつくりたい。高校生がこんなに頑張っているんだってところを、みんなに見てほしいんです。
ひとつのきっかけをつくる大和当帰
保科さんのチャレンジは製品づくりにとどまらない。昨年は推古天皇が薬狩りを行ったとされる、高取町と宇陀市で「薬狩りモニターツアー」を開催した。
大和当帰を収穫したり、料理を食べたり、薬草ワークショップや薬狩りの名所を巡る「薬狩散策」をするなど、地域文化や薬草について学び体験するこのプログラムは、早稲田大学「医学を基礎とするまちづくり研究所」と奈良県立医科大学とともに実施。「農村健康観光」の研究の一環として行われ、モニターツアー中に参加者の健康状態を測定し「農村健康観光」のさまざまな効果も検証していく、新しい試みだ。
 写真提供:早稲田大学「医学を基礎とするまちづくり研究所」
写真提供:早稲田大学「医学を基礎とするまちづくり研究所」
保科さん 高取にいる企業としても、農家としても、地元に根差したことはもちろんやりたい。だけど、もう少し奈良県全体として取り組むようなことができたらとも思います。
一般的な田植え・稲刈り体験だけでは、他の地域でやっているものとあまり変わらないので、もう少し特色を出そうと、昨年からストレスケアとかメンタルヘルスケアと連携した企画を始めたんです。臨床心理士の先生に監修していただいたり、漢方の先生に協力していただいたり。農業体験の効果を機器測定してくれたり、論文にまとめてくれたりして。その一環が「薬狩りモニターツアー」なんです。
高取町、宇陀市、キハダのある山添村、吉野。せっかく奈良県いろんな場所で薬草が栽培されているので、「農村観光健康ツーリズム」として県内に広がりがつくれるんじゃないかなって。今まで点であったものをつないでいきたいなと思うんです。
その想いを支えるのは、大和当帰生産農家のコミュニティ。大和当帰の生産農家は、普通であれば企業秘密という部分もオープンにして、互いに情報交換し合っているという。そんな関係性を築けているのは、信頼の力だと保科さんは話す。
保科さん それってきっと行政にはできにくい部分で、民間の僕たちだからできることなのかなと思っていて。まちづくりとかに携わらせてもらうと、よく「連携」とか「枠を超えて」とか聞くけれど、互いにルールがあって、枠を超えるってなかなか難しい。行政だからできることとできないことがあるし、民間だからできることとできないことがある。枠を超えてではなく、お互いがフォローしあえればいい。
そのひとつのきっかけをつくるのが大和当帰なのかなって。古くからあるけど、新しくてまだまだこれから可能性があるし、みんなが一緒に大和当帰をブランドとして育てていくチャンスが、今あるんかなって。それを通して奈良県内が全部つながっていけたら面白いかなと思っています。
いろんな人たちと関わるなかで見えてくる「気づき」

最後に、今後取り組んでいきたいことについて聞くと、こんな答えが返ってきた。
保科さん 当分は、大和当帰を中心にしながら、いろんなことをやれたらと思っています。ただ、大和当帰じゃないとだめって訳でもないし、キハダじゃないとだめって訳でもなくて。いろんな人たちと関わるなかで、見えてくる気づきみたいなものがあって、それを大事にしたいなと思っていて。
それは農家さんの困りごととか、こんなことができたらいいなという想いとか。そういうことに気づいた時に、そこに答えていくという風にしたい。たぶん一年後にまた話したら、違うことを言っているかもしれないんですけど(笑)。今はそこをちょっと大事にしていたいなと思ってます。
「ちょっと植えてみようか」の気持ちから始まった、大和当帰の栽培。さまざまな関わりやタイミングのなかで、大和当帰も保科さんの想いも少しずつ広がりを見せている。いつも周りに目を向けているからこそ、気づきが生まれ、新たな取り組みにつながっていくのだろう。みんなで補いあって、手を携えていけば、今まで見えなかった未来が見えてくるかもしれない。
この町で蒔かれた種が、多くの手によって温められ、芽吹く日がとても楽しみだ。