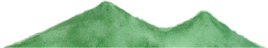たまごっておもしろい! 明日香村の「のらのわ耕舎」で生まれる、正直なたまご。
写真・文=森裕香子
イラスト=青木海青子(人文系私設図書館Lucha Libro)
山に囲まれた鶏舎のなかで、のびのびと過ごす鶏たちの元気な声が聞こえる。
明日香村で養鶏と農業を営む「のらのわ耕舎」の中村彰宏さんは、約500匹の鶏を平飼いで育てている。中村さんが選び抜いた、添加物や薬剤などを一切使用しない安全な餌を食べて育つ、健康な鶏たち。そのたまごはとても綺麗なレモン色をしていて、初めて見た時、その淡く優しい色合いに驚かされた。
なぜ養鶏を生業にしようと思ったのか。なぜこんなにも餌にこだわりぬくのか。なぜ黄身はこんな色をしているのか。お話を伺うと、そこには真面目で真っ直ぐな中村さんと、透明で正直なたまごの姿があった 。

中村 彰宏(のらのわ耕舎)
大阪府出身。京都で庭師を経験した後、子どものアトピーをきっかけに農業に転身を決める。2011年に奈良県明日香村へ家族で移住し、養鶏を中心に野菜とお米を生産する「のらのわ耕舎」を設立。https://noranowa.official.ec/
諦めようとした時、たどり着いた場所
中村さんが30歳の時、息子さんにアトピーがあることが分かった。「少しでも症状を軽くしてあげたい」と方法を探し、行き着いたのが食べ物を精査することだった。
食べ物が変わると、アトピーの症状は大幅に軽減され、改めて食べることの大事さを実感するものの、そういった食べ物は値段が高く、エンゲル係数が信じられない数字になってしまったという。「どうやってこの生活を続けていったらいいのだろう」。思い悩んでいた時、奥さんからの「思い切って農業やってよ」の一言が起爆剤になった。
そこから、中村さんの人生は大きく転換することになる。

その頃、僕は植木屋をしてたんですけど、限界も感じていて。別のことを考えようかなっていう時に、タイミングよくそんな一言があって。でも僕は、実はうどん屋がやりたいって思っていたんです(笑)。それなら、できるだけ無農薬で、素材から自分でつくるうどん屋を目指そうという話に落ち着いて、まず小麦の農園を訪ねることにしました。でも、いざ訪問してみると、その方は小麦づくりを辞めて養鶏をされていて。そこで初めて養鶏というワードに出会って、「どういうもんなんやろ、おもしろそうやな」って。そのまま研修させてもらうことになりました。
養鶏の知識などまったくない中、鶏が過ごす環境を改善してみたり、餌のバランスを工夫してみたりと試行錯誤を繰り返してみる。すると、鶏の状態もたまごの状態もみるみる変化していったという。
手をかけた分だけ鶏は応えてくれる。それがたまごにもストレートに表れるおもしろさに、どんどん引き込まれていく。何よりも、鶏が毎日何を口にしているのか、その口にしたものはどこからやってきて、どんな環境で育まれたものなのか、自ら把握できるというのは、中村さんにとってとても大きなことだった。
栄養バランス、餌の配合、素材の安全性、調べれば調べるほど発見と疑問が生まれていく。自ら納得できる素材を選び、安心・安全なたまごをつくりたい。中村さんは、養鶏を前提にした農業で独立しようと決心する。

養鶏でやっていこうと決めた一番の理由は、たまごってものすごく直接的なものやと思ったから。例えばマジックインキを入れた餌と、入れてない餌を交互に与えたら、マーブル模様の卵黄ができるくらい、油に溶け出すような成分は直接卵黄に移ってしまう。僕はもともと食に関心がない人間だったので、そんな概念がまったく自分の中にありませんでした。逆に、食に対して意識の高い家庭で育っていたら、ここまで興味が湧かなかったんじゃないかと思います。
研修を受けながら、養鶏と農業の両方ができる場所を求め、兵庫・岡山・京都・愛知など各地を探して回る日々。一年以上が経過しても見つからず、「諦めるしかないのか」と考え始めたとき、幸運にも現在の場所と巡り合う。2011年、明日香村の地で養鶏と農業を複合的に行う「のらのわ耕舎」をスタートした。

説明できない素材は使わない
平飼いの鶏舎はよく換気され、日光が入り、鶏たちはのびのびと走り回る。
床に敷かれた籾殻の上を鶏たちが自由に走り回ることで、籾殻と鶏糞が攪拌され、発酵し、自然に肥料ができる。その有機肥料を田んぼや畑に施し、育ったお米や野菜が鶏たちの口にも運ばれる。「自然の循環を大切に、鶏と野菜とお米を良い関係でサイクルし続けていけたら」と中村さんは話す。
今は外国が穀物を輸出してくれているから、日本の畜産はまわっているけれど、ある日突然輸出がストップしたら、その瞬間からまわらなくなる。でも、素材を生産してくれている人たちと連絡が取り合える関係で、売る・買うの約束がきちんとできていれば、普通に続けていける。それがなによりも安心だと思う。この土地で育まれた、顔の見える確かな素材を使って、お客さんに手渡しできる安全なたまごを素直につくり続けたい。そこは僕らが意地でも守らなあかん部分やと思っています。

そもそも、僕は“こだわり”って言葉がすごく苦手で。“こだわり”って我慢してでも貫くようなイメージがあるんだけど、たとえ今まで選んできた素材でも、安全性が確保できないんやったら使えない。「絶対にこれを使い続ける」ってこだわると、身動きがとれなくなる。
ひとつの素材にこだわらないで、その時期に採れるもの、手に入るものを探して、試して、工夫する。ちょっと変な言い方ですけど、唯一こだわっているのは、もう絶対的な「安全性」だけ。誰が、どこで、どんな方法で育て、採れたものなのか。どの角度から聞いてもらっても、ちゃんと説明がつくものしか使わない。そこはもう意地でも貫こうと決めています。

のらのわ耕舎の鶏たちの食生活は、栄養満点で、安全で、おいしそう
のらのわ耕舎の餌には、とうもろこしが入っていない。
日本の養鶏の多くは、餌に輸入とうもろこしを使っている。安価で、栄養が豊富で香りもいいからだ。ただ、輸入とうもろこしは収穫後、虫が湧かないように「ポストハーベスト」といわれる薬剤が散布されたり、遺伝子組み換えのものが多かったり、安全性が確かとは言えない。
こうした背景から、のらのわ耕舎ではとうもろこしは使用せず、自家栽培のお米や紀伊半島産のお米、奈良県産の小麦、明日香村で刈った野草や野菜の葉(緑餌)、腐葉土、高知県産の宗田節、広島県産の牡蠣殻、ポストハーベストフリーのトルコ産のごま、富山県産の大豆、奈良県の醤油屋さんの醤油かす、奈良県のお豆腐屋さんのおからなど、出来るだけ近郊の、中村さんの目で確かめた安心で安全な素材を配合している。

「とにかく仕入れに追われる」と中村さんは笑う。
普通なら、餌屋さんに電話して全部持ってきてもらうけど、うちやったら「おからが足りへん」ってなったら取りに行って、「もうすぐ小麦がでるよ」ってなったら取りに行って。今配合している中で、餌屋さんで買えてるのは牡蠣殻だけなんです。鶏の世話や出荷準備、餌づくり、田んぼや畑の作業をしながら、常に走り回っている。仕入れて使ってまた仕入れての繰り返しです。
たまごの安心は、黄身の色にあらわれる
集められた素材は、それぞれ粉砕や発酵を施し、混ぜ合わせ、仕上げにさらに発酵させて、ようやく鶏の口に運ばれる。その日の鶏の様子や、温度、環境に合わせて配合バランスを決めるため、たまごの味や色味も変化するそうだ。
そんな、のらのわ耕舎のたまごは、黄身の色が淡いレモン色をしている。黄身の色は鶏が食べたもので決まるため、実は何色にでも操作できるのだという。
日本人が黄身の色を気にするようになったのは、ここ20年くらいのことで、“オレンジの濃い色をしたたまごの方がおいしい”というのは、実は完全な思い込みである。一般的なたまごは、とうもろこしを餌とするため、黄身の色はオレンジ色に近くなる。多くの養鶏場では黄身の色をわざと濃くするため、パプリカやマリーゴールドの色素を餌に加えていたりする。
黄身の色が薄いのは、新鮮な野草やお米を食べているからこその自然な色なのだ。

クセがなく、口に含むとさっぱりとした透明感のある味わい。
他の食材の味を邪魔しないので、素材の味や出汁の味が活きる和食との相性は抜群。
週に一度の会話から、続けていく原動力が生まれる
のらのわ耕舎のたまごを語る上で欠かせない存在がある。毎週金曜日の朝に開かれている「明日香ビオマルシェ」だ。中村さんをはじめ、安全でおいしいお米や野菜をつくる仲間たちが運営し、顧客と顔を合わせてコミュニケーションをとる大切な機会となっている。

毎週マルシェを開くのはやっぱり大変ですけど、毎週会えるからこそ、お客さんと関係や会話が続くし、疑問にも答えられる。やっぱり誰かが食べてくれるから、価値を認めてくれるから、嘘つかずに努力できる。食べて、喜んでくれる人がいるから、頑張れるし、それが原動力になる。もうそれしかないんです。僕は今できる精一杯をやりたいというだけだし、お客さんが疑問に思うことを取り除いていくことしかできない。僕も勉強させてもらっているし、満足せずにいられる。
ビオマルシェのように、相手の顔を見ながら会話できたり、共感しあったり、お互いの意見を共有できる場があることってすごく大きいです。お客さんの顔が見えないと、お客さんが何を求めていて、自分が何をしたかったのか、分からなくなりかねない。立場も年齢も性別もバラバラな、いろんな人が集まるビオマルシェは、さまざまに抱いている疑問や想いをちゃんと肌で感じることができる大切な場所なんです。
「決して儲かるわけでも、毎日の生活に余裕があるわけでもないけれど…」と、中村さんは言葉を続ける。
「養鶏めっちゃいいですよ」とか、人には絶対に言えないし、勧められない。でもたまごは正直だから嘘をつかなくていいし、自分がある程度、いろんなことをコントロールできる。その舵取りは、ちっちゃな養鶏や、ちっちゃな農業やったらできる。そうしていくと、見えてくるのは、やっぱりお客さんの顔なんです。お客さんの素直な声も聞かせてもらえるんで、ビオマルシェの存在はすごく大きいなって、つくづく思います。

わずかな餌の配合や、日々移り変わる気候によって、鶏の調子は顕著に変わってしまう。極端にたまごを産まなくなり、もう辞めるしかないところまで追い込まれたこともある。けれど、それでも養鶏を続けているのは「どこまでいっても終わりがない。飽きない理由はそこですね」と中村さんはひょうひょうと話す。
何度も何度も試行錯誤を繰り返し、時に仲間に救われ、時にお客さんに救われながら、生まれてくるのらのわ耕舎のたまごは、真面目で、安心できて、嘘をつかない、中村さんの人柄がそのまま表れたような優しい色をしている。