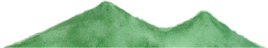明日香村では、6月に入るとあちらこちらで田植えが始まる。昔ながらの日本の原風景が残るこの地でも、田植えの作業はほとんどが田植え機で行われ、あっというまに小さな稲が植わっていく。

昔から、田植えは米づくりのなかでも大切な作業であると同時に、田の神を迎え豊作を願う神事でもあった。
早乙女(さおとめ)と呼ばれる女性たちが、唄をうたいながら稲を一株ずつ手作業で植えていく。早乙女たちがうたう「田植唄」は、秋の豊作を願い、祈りを捧げる役割であったが、重労働である田植えを楽しく飽きずに行う意味合いも強くなり、唄だけでなく、太鼓や笛のお囃子(はやし)や舞、踊り、曲芸なども合わさり、賑やかなものとなっていった。
現代では効率化が図られ、人手もかからず、時間も短縮される機械での作業が当たり前となったが、手植えでの作業とともに田植唄や踊りを継承し、後世に伝えようとする人々もいる。田植え神事や田植え祭りなどの行事が、大切に受け継がれている地域が今も日本各地に存在する。

明日香村に移住し農業を営む、「たるたる農園」の樽井一樹さんと「ミニマルライフ」の瀬川健さんが主催する「あすか田植え祭り」は今年6月23日(日)の開催で4回目となる。
 こちらが樽井一樹さん
こちらが樽井一樹さん
 臼に手をかけているのが瀬川健さん
臼に手をかけているのが瀬川健さん
“いのちめぐる畑”をコンセプトに、土の力を最大限に活かした野菜づくりを行う樽井さん。“余計なものを一切使わない”ミニマルという理想を元に自然栽培のお米づくりを行う瀬川さん。ふたりは「たるマルライフ」と称し、共に古代米づくりに取り組んでいる。
そんなふたりが主催となり、明日香村の棚田ではじめた田植え祭り。3回目の開催となった昨年も大勢の人が集まり、賑やかに田植えが行われた。


片手に苗を持ち、バランスを取りながら泥のなかへ。子どもたちも楽しそう。

田んぼの畦道で太鼓や笛の音が奏でられ、唄い、踊り、賑やかに囃したてられながら、稲が少しずつみんなの手によって植わっていく。


真剣、田植えレース。応援する子どもたちの声が和やかに響く。


田植えの後は、お餅つきも。“さなぶり餅”というもち米と小麦を合わせたお餅で、奈良の農家では田植えが終わったらこのお餅をつき、田の神様にお供えする。豊作を祈り、無事に田植えを終えたことを感謝しながらいただくのが習わしだったそう。


田植え祭りで植えられた稲は、数種類の古代米。なかでも「神丹穂(かんにほ)」という稲は夕日に照らされると穂が赤く光り輝き、夏から秋の変わり目の頃には、なんとも美しい光景が広がる。


ひと株ひと株、一人ひとりの想いが込められた美しい古代米は、食べるだけでなく、ドライフラワーにも。お飾りとして、スワッグとして、しめ縄としてなど、広がりも見せている。

わたしたちが毎日、毎食、口にしているお米。古来から受け継がれてきたお米づくりは、日本の文化の源で、それは食文化だけでなく、芸能だったり、地域みんなで助け合うことだったり、結びつきだったり、自然や土地を大切にすることだったり、米づくりからさまざまな文化や精神が育まれてきたんだろうなと、田植え祭りを通して感じることができた。
今年も、子どもたちのはしゃぐ声、唄声、音色に包まれ、賑やかな田植えが行われるだろう。
あすか田植え祭り2019イベントページはこちら
https://www.facebook.com/events/343691876347195/