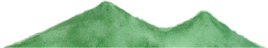「何したい?」
友人から「遊びに行きたい」と連絡が来ると、まずそう聞いている。山登りばかりしている生活を始めて6年目。地元を離れ、奥大和の山に囲まれた村に移住して2年目になる。
環境のせいもあり、山登りばかりしている生活は、山登りしかしていない生活へとエスカレートした。そんなわたしの様子がおもしろいのか、あちこちから毎月のように友人たちが遊びに来る。わたしは連絡をもらうと、友人たちの登山の力量と好みを考えて「こんなことしてみる?」と山遊びの計画を提案している。
あるとき、前職の先輩から「遊びに行ってもいい?」と連絡が来た。全くの登山初心者だったわたしを、日帰り登山からテント泊縦走まで、一通りのことをできるように仕込んでくれた恩人だ。
これは張り切っておもしろい提案をしなければと、自分の頭の中にあるデータベースを検索しているうちに、ある計画が思い浮かんだ。大峰山脈の「大普賢岳」と台高山脈の「大台ヶ原」をつなぐ縦走である。長く歩くのが好きな先輩にぴったりに違いない。それは以前、時間切れとなり途中敗退した計画だった。
提案したのはその続きで、前回下山したところから台高山脈の大台ケ原までを歩き通す1泊2日の山旅である。計画を伝えると、案の定二つ返事で話に乗ってくれた。

「それにしても、だいぶ山奥だねえ、びっくりしたよ!」
村に着いた先輩は驚きを隠せない様子だった。コンビニやスーパーがないことや、鹿が道路に飛び出してくること、信号は2つしかないことなどを事前に伝えてショックを和らげたつもりだったが、おそらく想像を超えていたのだろう。どんどん山深くなっていく景色に、運転しながら本当に人が住んでいるのか不安になったそうだ。
合流した後、いったんゴールとなる大台ヶ原の駐車場へ車を一台回送してから、別の車でスタートになる登山口へ向かった。
荷物は1泊2日分の食料と「ツエルト」と呼ばれる簡易テント、シュラフ(寝袋)、衣類、緊急の時に必要なものなど最低限にした。軽くすることでスピーディに動くことができ、体力の消耗も抑えられる。また、荷物を吟味することで、工夫しなければいけないことも増える。要するに、減った荷物の部分を自分の知識と経験で補う必要があるのだ。
そういう準備段階からのシミュレーションは、初めてのところへ出かける時の探検気分を盛り上げてくれる。わたしと先輩は、いつもより少し軽めの荷物で足取りが軽いことを感じながら、秋の森へと足を踏み入れた。

「この左側はわたしが住んでいる村なんですよ。」
歩き始めてしばらくすると、尾根上にある村と村の境目に出た。地面に刺さった杭がそれを示している。そこは、杭を境に針葉樹の森と広葉樹の森にくっきりと分かれていた。針葉樹の森は暗く広葉樹の森は明るい。わたしが住む村は500年続く吉野林業の発祥の地だ。

普段家の周りで目にする森は針葉樹がほとんどで、神殿の屋根を支える柱のようにまっすぐ天に向かってそそり立つ姿は神秘的ではあるが、湿っていて薄暗い。それに比べて広葉樹の森は木漏れ日が入り、足元はフカフカの落ち葉。いろいろな樹種が自由に枝を伸ばしていて開放感がある。

「広葉樹の森はきれいだなあ、明るいなあ」
紅葉した木々を見上げながら、そういえば、そんなふうに思うようになったのは、村に住むようになってからだなと気がついた。
歩き始めて数時間。陽は傾き、西日が広葉樹の森をさらに明るくオレンジ色に染めている。
「この辺にする?」
先輩が足を止めてあたりを見回した。気がつけば目指していた今晩の寝床の候補地についていた。広葉樹の落ち葉が敷き詰められてフカフカした地面は、心地よい自然のマットレスになりそうだ。
「今夜は快適に寝られそうですね」と、わたしはリュックを下ろしながら答えた。それぞれツェルトを設営して、寝る準備が整うと、お湯を沸かし、お茶を飲む。そのあと夕食をつくり、食べながらたわいもない話をして笑った。

「本当に奈良に住むと思わなかったよー」と先輩はいつもの弾むような声で言った。
わたし自身もあんまり考えていなかったし、いまだに自分の状況をよくわかっていない。移住者と言われるとなんだか荷が重い。自分のホームマウンテンならぬホームフィールドが欲しいと思ったというのが、動機として一番近い。
以前から、この奥大和を含めた紀伊半島は、思いつく限りのアウトドア・アクティビティができる場所だと目をつけていた。ハイキングやトレッキングはもちろん、沢登り、キャニオニング、ケイビング、トレイルランニング、クライミング、ボルダリング、カヌーやカヤック、海の方へ出ればサーフィン、シーカヤックも可能だろう。
冬は雪が降り、滝も凍るから雪山登山やアイスクライミングもできる。山の形状や季節に合わせて「何をして遊ぶと一番おもしろそうか」を考え、実行することに最大の喜びを感じるわたしにしてみれば、ここは潜在的な可能性をまだまだ隠し持っている。それを知るには、その土地に拠点を持つべきだと思うようになったのは自然なことだったのかもしれない。
夕闇が迫る森の奥で鹿が鳴く声がした。「そろそろ寝ましょうか?」わたしたちはそれぞれの寝床に潜りこんだ。
—–
寝袋のまま寝返りを打つと、外が明るくなっていることに気がついた。ツェルトから這い出ると、朝方降った雨のせいか、霧が残っていて景色は幻想的なものになっていた。

深夜、猛ダッシュしてきた鹿が危うくわたしたちのツエルトにぶつかりそうになって、急ブレーキで止まったような物音がしたと先輩が言っていた。どうやら鹿の通り道に寝床を構えてしまっていたようだった。
手早く朝食をとり、ツェルトをたたみ、全てをリュックに入れて背負うと、わたしたちがそこにいた痕跡は、四角く残る乾いた落ち葉の地面だけだった。

歩き出してしばらくすると霧は晴れ、景色が見通せる場所に出た。遠くに小さな集落が見える。
「あんなところにも人が住んでるんだね」と先輩が言った。
「そうですね」と、わたしはまるで他人事のように答えた。
自分がまだ、この村に住んでいる実感がない。ただ、わたしはわたしなりの方法で、この土地に住みながらこの土地を楽しんでいる。それがどれだけ続くのかはわからない。日々を積み重ねていくだけだ。
でもそれを見たいと言って、遠くから友人が訪ねてきてくれる。それが今のわたしが出せる答えのひとつなのかなと思ったりもしている。
(※朝日陽子さん執筆の別の記事はこちら)
Writer|執筆者


朝日 陽子Asahi Yoko
愛知県出身。芸術系大学を卒業。アパレル会社に勤務後、登山用品専門店に転職。アウトドアを通じての町おこしに興味を持ち、2017年より地域おこし協力隊として奈良県川上村へ移住。現在は県外在住。