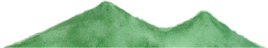川上村での暮らしが私に与えてくれたこと
写真・文=百々弥薫
自然豊かでやさしい環境を求めて
日本が大きく揺さぶられた2011年。私は赤ちゃんを授かり、夫の実家がある奈良に引っ越し、結婚し、出産した。やがて子どもが2人になり、想像をはるかに超えた子育ての大変さを噛みしめながら、なんとか必死で暮らしていた。
長女が5歳、長男が3歳の時、大阪まで勤めに出ていた夫が、川上村の「匠の聚」という施設に転職すると言い出した。
川上村ってどこ? どんな仕事するの? 大丈夫?
私の頭の中はクエスチョンだらけだったが、なんとなくおもしろそうな気もした。
でも、子どもたちはまだ手がかかるし、特に息子には生まれつきの障害とアトピー、食物アレルギーがたくさんあり、当時の生活でさえ余裕があるわけではなく、よく知らない場所に暮らしの場を移すなんてリスクが大き過ぎると思った。夫の仕事だって続くかどうかもわからない。「1年間は今の家から通ってほしい」と夫に伝えた。
ある日、「とりあえず一度見に行ってみよう」と家族で川上村に出かけた。夫や義父は川上村や「匠の聚」とは何年も前からご縁があり、私もそういえば結婚前に夫と何度か訪れたことを思い出した。当時住んでいた広陵町からは1時間半もかからないくらいだが、吉野のさらに奥、朧げな記憶ではとにかく遠く、何もないイメージ。かつて林業で栄えた山間の村。僻地と呼ばれる地域だということは後で知った。
トンネルをいくつも通り抜けて川上村に入ると、雄大な山々が私たちを迎えてくれた。

国道から見える景色はほぼ山と川。役場の周辺にホテルや小さな道の駅、保育園などがあるが、スーパーもコンビニもない。圧倒的な自然の存在感に対して私たち人間がとてもちっぽけな存在に思え、そのことに不思議と安心感を覚えた。
スピードや効率重視でシステム化され、人間がすべてをコントロールできると錯覚するような現代の価値観や、決められたルールに合わせ自分を押し殺して生きていくことに、私自身生きづらさを感じていたし、そんな社会を子どもたちに手渡していくことにも疑問を感じていた。
私は、子どもを産み、子どもと生活をするうちに、自然が豊かで、顔と名前のわかるご近所さんが温かい声をかけてくれるような、そんな環境を求めるようになっていた。川上村のその大きな自然は、居場所のない私を受け止め、ゆとりのある子育てや暮らしを叶えてくれるような、そんな気になり、帰る頃には「すぐにみんなで引っ越そう」という言葉が口を突いていた。
移住
2017年4月、私たちは川上村に移住し、村の中でも東部に位置する「白川渡(しらかわど)」という地区で暮らすことになった。国道から脇に入ってすぐ、清流が流れる川沿いに建てられたばかりの村営住宅を運良く借りることができた。

村の人口は1500人ほど(実際住んでいる人はもっと少ないという)で、もちろん少子高齢化が深刻。人が少ないためか、「この村では全員知り合いか?」と思うほど、「○○の集落の○○さんが」とか、登場人物みんなに名前があり、なんだかサザエさんのような世界だと思った。
最寄りの小さな商店までは30分ほど。買い物は週1回になり、気軽に出かけることは少なくなった。それでも暮らし始めて名前と顔を覚えてもらうようになると、野菜や川魚、手作りのこんにゃくや佃煮など、色々といただくようになった。
村の面積のほとんどが山で、村内に田んぼは一枚もないけれど、村の人たちは小さな畑で野菜を育て、山の幸を受け取り、色んなものを手作りしている。当たり前のように昔からの知恵を受け継ぎ、手と足を使って工夫しながらひとつひとつ紡いでいく、そんな暮らしぶりに尊敬と憧れの念を抱いた。
そして、日常茶飯事で行われる「与える」「受け取る」「感謝する」「お返しする」の循環には、思いやりや分かち合う心、助け合う精神が宿っていて、いつも胸が温かくなった。
同じ集落で30近い世帯のうち、子どもがいるのは我が家も合わせて3世帯だけ。娘の同級生の女の子が、引っ越してすぐに遊びに来てくれた。子どもたちはすぐに仲良くなり、家族ぐるみの付き合いをさせてもらうようになった。

引っ越すに当たって1番の不安だった「週末子どもたちとどうやって過ごそう」という問題もすぐに解決したし、息子のことも自然に受け入れてくれる人ばかり。この人と人との距離の近さや人間関係の濃密さが私にはとても心地よかったし、人の温かさが本当にありがたかった。
かあちゃんトンビになりたい
村にはひとつだけ保育園がある。その「やまぶき保育園」に通う園児は20人ほど。奇跡的に息子も加配の先生についていただけて、お姉ちゃんと一緒に通園できることになった。
引っ越してしばらくした頃、私はよく、空を悠々と飛ぶトンビを見て「かあちゃんもあのトンビになりたいわ〜」と口にした。すると娘に「えー、そしたらおっぱいあげたり、オムツかえたり、はーちゃんとこたくんを寝かせたりできへんよぉ〜」と言われて笑ってしまった。

自由になることに潜在的に憧れていながら、この頃の私は自分のことは後回しで、考えるのは家族が健康で元気に過ごすためにできることばかり。障害を持って生まれた幼い息子に対する自責の念が、まだ私の中で大きく存在していた。
祈るような子育て一色の数年。得意ではない家事を自分なりにがんばり、より健康な食事を手間暇かけて用意した。そして息子もようやく毎日保育園に通えるようになった頃、私は数年振りに静かなひとりの時間を過ごすことができた。
保育園の送り迎えで車を走らせる度、否応なしに目に飛び込んでくる、日々移り変わる荘厳な風景や、洗濯物を干しながら感じるじんわり頬を照らす太陽の温かさ、山の谷間を通り抜ける風の厳しさ、畑に向かう隣の集落のおじいちゃんとおばあちゃんとの会話。ひとつひとつが新鮮で、私を優しく包み込んでくれるようだった。

ただ感じるという時間。自分の感覚を意識する時間があまりに久しぶりで、なんだかリハビリのようにも感じた。本来それが自然であることを少しずつ思い出していたように思う。
また、月に一度、村の小学生のお母さんが開催する青空ヨガ教室に通った。ヨガは独身の時以来で、身体も硬かったり、動きもぎこちなく感じたが、一番驚いたのは呼吸を意識する時間だった。
ゆっくりと、長く長く息を吐き、吐き切ってから息を吸う。自分の呼吸を意識することなんてずっとなかったように思うが、こんなにも深く呼吸をし、静かに自分を感じる時間を過ごしていいものなのかと衝撃を受けた。北和田地区の小学校跡で、私の肺を満たすその透き通った空気は、私を身体の内側からも癒してくれた。自分の身体と感覚を、誰のためでもなく、自分のために使う時間との出会いだった。
移住者同士の交流の中で
念願の田舎暮らしが叶い、ある意味悠々自適に過ごす私とは逆に夫はストレスがあるようだった。
子どもの頃からそれなりに便利な環境で育ち、大人になってからもずっと東京や大阪で仕事をしてきた夫にとって、川上村での暮らしは色々なことが受け入れ辛かっただろう。募るストレスを私にぶつけてくるような時期もあり、夫婦のすれ違いのようなものがどんどん膨れあがっていった。
そんなある日、この村で知り合った友人家族が遊びに来てくれていた。
子どもたちが寝静まってしばらくすると、何がどうなったのか、いつの間にか私たちの夫婦喧嘩の公開裁判が始まっていた。どこまでも平行線で交わらない私たちそれぞれの思いを、友人たちがひとつひとつ受け止めてくれたのだ。弱みや醜態をさらすということは、恥ずかしいのは言うまでもない。でも、そのおかげで私たちは心を軽くすることができたし、冷静に、自分たちのあり方を考えるきっかけになった。
人はひとりでは生きていけないこと、人に話を聞いてもらうことの大切さを心の底から実感する。こうして、人に頼ることや甘えることを覚えさせてもらったように思う。
白川渡から東川への引っ越し
川上村で暮らして1年を迎えようとする頃、大きな出来事が起こる。息子がインフルエンザにかかったのをきっかけに、重いてんかん発作を発症するようになった。2018年の2月。ちょうど、川上村のすべてが雪に覆われた景色のように、私の頭の中は真っ白で、時間が止まってしまったみたいだった。

なんで?なんで?なんで?
本当に時間が止まってくれたらよかったけれど、息子のてんかんは止まらず、たびたび起こるようになった。吉野消防署から30分かけて駆けつけてくれた救急車にも乗ったし、奈良医大まで飛ぶドクターヘリにも乗った。
気が気じゃない毎日。何がいけなかったのか。
息子は保育園にも行けなくなり、私も楽しそうなイベントに出かけるのはもちろん、買い物にすらほとんど行かなくなった。それでも、よく家の近くを散歩した。夏には近くのキャンプ場にある小さな小川で遊んだり。時折り見せてくれる息子の笑顔に救われた。

そんな静かでささやかな生活の中、私に届いたのは、さらに深く、自分と向き合う時間だった。自分自身のこと、娘と息子が生まれてきてくれた意味。たくさんの気づきを得て、自分自身を癒すような時間を過ごした。
自粛生活は1年半近く続いただろうか。今でも、疲れやすい息子に合わせての暮らしが当たり前だけれど、私の捉え方や気持ちの持ち方・付き合い方など、色々が少しずつ変わっていった。
娘の保育園の送り迎えの際、顔馴染みのおかあさんたちとの挨拶や何気ない会話にいつも元気をもらった。みんなが、家族のように心配し、見守っていてくれていたから乗り越えられた。温かくて優しい人との繋がりに、本当に感謝しかなかった。

てんかんの症状にも少しずつ慣れ、川上村での2回目の夏が終わろうとしている頃、息子の通院の負担を軽くしようと、1年4ヶ月暮らした白川渡から川上村の入り口にある東川という集落へと引越しすることにした。村内の移動だけれど、車で30分ほど距離がある。家族みんなお世話になった白川渡の集落を離れるのはとても寂しかった。
地元の人との交流
村内と言えど、場所が変われば雰囲気も人も気温までも違う。私たちは東川集落の中の「柳瀬」という7世帯しかない小さな垣内で新たに暮らし始めた。
柳瀬では、集落の真ん中に突如建てられた村営住宅に入らせてもらったので、昔から続いている暮らしの中にひょっこりお邪魔させてもらうような感じだった。気持ちよく受け入れてもらえるか最初は少しドキドキしたが、温かく迎え入れて下さり、本当によくしていただいた。
ここでも、野菜や手作りのものをあれよそれよとくださったり、雨が降れば「降ってきたでー!!」と洗濯物や布団を取り込んでくださったり、息子と散歩をしていると「ちょっと寄ってき」と、縁側でコーヒーを出してくださったり。村のおっちゃん・おばちゃんたちとの交流が私たちの生活に彩りを添えてくれた。

「無いならつくろう」で始めた子育て広場
ある時、私たち家族の1年後に村に越してきた2人のお母さんたちと意気投合し、それぞれの自宅を開放して「子育て広場」を開催することにした。村には子育て支援センターや児童館のようや場所がなく、お母さんが子どもを連れて遊びに行く場所や、ゆっくり話をしたり情報交換したりする機会が中々なかったからだ。
子育てが決して楽ではないこと、これからの時代を生きていく子どもたちにどんな環境を用意してあげられるだろうか。そんなことを話し合いながら、子どものよりよい育ちのためには、まずお母さんが心から笑っていられることが大切だと、お母さんたちの癒しの場になればという思いで活動をスタートした。
飲み物やお味噌汁、おやつなどをその時々で用意して、参加する人も何か持ち寄っていただく、そんな小さな小さな循環の場。自分の胸の内を人に聞いてもらうことの大切さを感じていた私にとって、話を聞くことを大切にする時間で、笑顔になってもらえることは何よりの喜びだった。
ゼロになって創造する
私はどうしてここに来て、これから何をするんだろう?
漠然と考えていた時、匠の聚在住作家である日本画家の岸上ゆかさんの個展で拝見した言葉に強く惹かれる。
ゼロになって創造する。
水源地という水が生まれるこの場所に、私はゼロになるために来たのではないか。生まれる前なのか、生まれた時なのか、ただ存在するワタシという存在に還り、それからきっと、何かを創造するのだろう。そんなことを感じていた。
今、私は誰かの人生を応援するということをしたい。そんな自分を、この村で見つけることができた。私が私の役割を生きること。そこに向かう私の学びと歩みを、山の神様たちに見守っていただいたように思う。
息子の就学先の選択の末に
「障害のある子の小学校就学時は選択に迷う」と聞いていたが、本当に迷った。「地域の小学校に通うのが自然なことなんじゃないか?」「専門的に支援してもらえる方がいいのでは?」それぞれの考えが波のように寄せては返した。
そもそも地域の小学校に受け入れてもらえるのだろうか。町の特別支援学校に川上村から通うのは息子の体力的に難しい。せっかく出会えた、たった3年だけれど築いてこれた私たちの居場所を手放したくない。
家族で何度も話し合い、教育委員会の方や、小学校の先生たちとも話し合いを重ねた。私も夫も、感情的になってしまうこともあったけれど、でも、「川上小学校に来てもらえるなら最大限努力します」と言っていただけたことで、「ここにいてもいいんだ」と、私たちはようやく安堵することができた。
そこから、この先のこと、息子のこと、家族それぞれのことを冷静に考え、最終的に特別支援学校への就学を選び、川上村を出ることを決めた。

これからも大切にしたい私たちの第二の故郷
村を出て感じるのは、できることなら、今も、村全体がひとつの大きな家族みたいなあの場所にいられたらよかっただろうな、ということ。川上村でこれからも暮らしていける人たちを羨ましく思う。

でも、寂しくはない。いつでも帰れるから。
いつでも、暖かく迎えてくれる家族のような人たちがいる。「第二の故郷」という言葉があるけれど、まさにそういうことだと感じている。それが私にとって、私たち家族にとって、どれだけ心強く有り難いことか。ありがとうの想いが、何度も私の胸の中でこだまする。
自分と向き合い、ゼロになって、ようやくスタート地点に立ったような気がしている。これからまた、たくさんの挑戦と失敗を重ねて何かを創造していくのだと。川上村で過ごした時間は私に本当にたくさんの出会いと気づきを与えてくれた。
不便という意味で、日常的にロックダウンしているとも言えるような僻地の村には、私が知らなかった豊かさがあった。川上村に移住してすぐの頃、先に移住してこられていた方と「ここはとても豊かで、時代の最先端ですね」という会話をしたことを覚えている。
その言葉の通り、たくさんの魅力と可能性を秘めているように思う。奥大和の地の魅力が多くの方に伝わっていくと嬉しい。
Writer|執筆者


1986年、三重県生まれ、高取町在住。地域情報誌の営業と編集に携わる。2011年に結婚・出産し、2017年に川上村に移住。子育ての傍ら、人が自分らしく生きることを応援する活動をスタート。