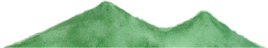毎週土曜日、僕の住む川上村では「やまいき市」による朝市が開かれる。
この「やまいき市」は、川上村で地域資源を活かした仕事づくりを目指すプロジェクトの名称だ。僕を含む地域おこし協力隊3名で活動し、現在は主に、地域の野菜を活かそうと取り組んでいる。
野菜の生産者である地域の方々は、土曜日の朝になると野菜を袋に詰めて値段と登録番号のシールを袋に一つずつ貼り付け、数量と金額を記入した伝票をつくる。おすすめの調理方法や追加のお知らせをメモに書く人もいる。そして、近所のスーパーから借りたカゴに野菜を集め、僕らの軽バンを待つのである。

80歳や90歳を超えた人も、毎日のように畑でコツコツ働いて、毎週野菜を出してくれる。集荷に行くと「悪いけど、今日これしか出せへん」と、その人は挨拶がわりに言う。伝票とカゴの中身を確認しているあいだ、軽バンの後ろの方から「上等な白菜!本当に上手につくっとる」という元気な声が聞こえる。確認を終えたら、僕らは野菜を車に載せて次の家へと急ぐ。
「やまいき市」の代表である岩本寛生は、別の軽バンで別の地区の野菜を集荷して、西河地区の朝市会場へやってくる。
 この赤い服を着ている人が岩本さん
この赤い服を着ている人が岩本さん
そこで僕らは合流し、市場を開く準備を開始する。大きな白いテントと木製のテーブルを立てて野菜を並べていると、常連のお客さんが車で乗り合わせてきたり、ぼちぼち歩いてきたりして、営業開始前からほしい野菜に狙いを定め始める。
夏はきゅうり、秋は芋類、冬は白菜と大根が大きな山になるが、生産者の腕のおかげで、どの季節も色とりどりの品が揃う。やがて、普段もの静かな岩本さんの「どうぞ、お買い物してください!」という大きな掛け声で、朝の買い物ラッシュが始まる。

経験豊富なお客さんはそれぞれ野菜を細かく見比べ、都会から来たお客さんは山菜を見て「すごい!イタドリだ!」などと興奮する。地元の人が「そんなん、その辺にいっぱい生えてるで!」と伝えると、都会の人は大抵びっくりする。「まいど、すみませんな」とお客さん同士はよく挨拶し、久しぶりに会った人たちは30分ほど立ち話をして帰っていく。
生産者とお客さんの力をつなぐのは岩本さんだ。彼は野菜の集荷だけでなく、会計や仕入れなど「やまいき市」のあらゆることを管理している。よくしゃべるタイプではないが、彼と話してみると、「やまいき市」が大事なのだと分かる。

スーパーもコンビニもない川上村では、この朝市が買い物できる場所として役立っている。生産者にお金が回るということもとても素敵だ。たくさん儲からなくても、野菜の販売だけで過疎化の問題が解決できなくても、「やまいき市」は人を集める賑やかな場所だ。
畑仕事がなかなかできない僕にとっては、毎週の朝市で野菜を買うのが一番効率がいい。冷蔵庫が旬の野菜でいっぱいになって、一週間でちゃんと使い切ることがいつもの課題。僕は冷蔵庫から野菜を出すたびに、登録番号のシールを見て、「〇〇さんのほうれん草だ」や「〇〇さんの大根だ」と意識せずにいられない。
もちろんどれも新鮮でおいしい。料理の素材が、誰によってつくられたものかを知ることは、うちの食事に新たな次元を与えてくれる。

夏が暑くても、冬が寒くても、やまいき市の生産者は植えた種の実りを毎週収穫して、僕らに出してくれる。生産者がよく「野菜の集荷や販売が大変そうだ」と言うが、一年中畑で働くことの方が随分難しそうだと思う。
朝のラッシュの後、お客さんがだんだん少なくなる。最後に残った野菜を数えて、伝票に記載してから、岩本さんと僕はそれぞれ返却に向かう。
僕は暗くなった高原地区に着き、家から家へ、伝票と一緒に売れ残った野菜を返却する。「寒かったやろう!」と一人のおばあさんは玄関へ出ながら言った。
「全部売れましたけ?ご苦労さん、ご苦労さん」。
慌てている朝と違って、夕方はゆっくり話す時間がある。岩本さんは最後のお宅のおばあさんと一緒に座って珈琲を飲みながら、お話をする習慣を持っている。

僕らはその人たちの孫とあまり変わらない年齢だから、お菓子や一品料理をよくもらう。顔が違っても、自分のおばあちゃんと同じような雰囲気を持っている人が何人もいる。(僕のおばあちゃんは92歳で、アメリカのオークランド市にある家の庭でパスタソースの材料を育てている)。帰り道、そのおばあちゃんにいただいたお菓子をかじるのが、毎週の小さな楽しみだ。