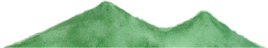あなたは『新十津川物語』を読んだことがありますか?
『新十津川物語』は、奈良県五條市出身の作家・川村たかしさんが実に15年以上の歳月をかけて綴った、全10巻の児童小説です。明治22年、十津川村を襲った未曾有の大水害によって、両親も、住む場所も失った9歳の津田フキは、北海道への移住を決めた2500人の内のひとりとなって、新天地を目指しました。
十津川村での災害、過酷を極めた原生林の開拓、北の大地での出会いや別れ。さまざまな困難に直面しながらも、家族や友人、動物たちと助け合いながら、優しく、たくましく生きていくフキの一生が、明治・大正・昭和の激動と共に描かれています。
そんな『新十津川物語』はどのようにして生まれたのか。川村たかしとはどんな人物だったのか。氏と共に人生を歩んできた妻の喜津子さんにお話を伺いました。

川村たかし
1931年、奈良県五條市生まれ。奈良学芸大学卒。第3代日本児童文芸家協会会長。五條市名誉市民。紫綬褒章、旭日小綬章を受章。五條市の小・中・高校教諭を経て、奈良教育大学、梅花女子大学教授を歴任。1978年、『山へいく牛』で国際アンデルセン賞優良作品賞・野間児童文芸賞を受賞。1980年に『山へ行く牛』『北へ行く旅人たち-新十津川物語』で路傍の石文学賞、1989年に『新十津川物語』(全10巻)で日本児童文学者協会賞・産経児童出版文化賞大賞を受賞するなど、多数の文学賞に選ばれる。2010年1月30日、逝去。

川村喜津子(かわむらきつこ)
奈良県五條市生まれ。聖イトオテルミー学院・名誉講師。長年、民間療法である「イトオテルミー療法」の普及に努める。夫・川村たかし氏の志を継ぎ、十津川との縁を紡いでいる。
物語は十津川大水害から始まる
全10巻、原稿用紙にして実に4000枚を超えた長編小説は、明治22年8月の十津川大水害の予兆を感じ取ったいかだ師たちの、ヒリヒリとしたやり取りから始まる。
電気も機械もまだない時代。
空は分厚い雲に覆われ、月明かりも地上にはほとんど届かない。山中で聞こえるのは、人間の話し声と生活音、そして動物たちが森の中を歩き、鳴く、命の音。その暗闇の中、「ことぼし」という小さな灯りがフキの家の中を薄く照らしている。やがて雨が降り出し、雨足はだんだん激しさを増していく。
三日三晩、降り続く雨。やがて山のあちらこちらから丸太ほどもある水柱が噴き出し、次々と異変が起こり始める。
–家がキシキシと鳴った。囲炉裏の上で自在鉤が大きく揺れ始めている。外へ目を戻したフキは、目の前の山がひょいと動いたように思った。谷をへだてた高い山の空が、ふっとずれて動いたのだ。あれっと思った時、足の下でやわらかいものがぐにゃりとうねった。不快感が突きあげてきた。家鳴りはまだ続いている。彼女は入り口の柱につかまって、「お母ちゃん」と、叫んだ。
「地震やよ。」 とたんに、ずうーんと大きな衝撃が来た。中にいたものもあわててとびだしてきた。ひさしの下に雨をさけながら目をこらす。そして、みんなは息を思わず飲んだ。右手那智合川の下流へかけて、谷はなんともいえず赤かったのだ。 (新十津川物語 第1巻より)–
冒頭からおよそ70ページまでのあいだに、今まさに、目の前で事が起きているのではと錯覚するような臨場感で、山津波の様子が描かれる。その大き過ぎる自然の流れの一部となって、命を終える人々。不安、恐怖、悲しみ。次々と訪れる感情をその幼い体で引き受けて、9歳のフキは、それでも命を諦めずに生きていく。
この物語は、綿密な取材に基づく小説、すなわちフィクションだ。津田フキはじめ、登場人物は誰ひとりとして実在していないが、フキのような体験をしてなお生きた十津川人たちがいたというのは、紛れもない事実なのである。
川村たかしを小説家にした出来事たち
奈良県五條市にある、江戸時代の町並みを残す五條新町の一角に、川村たかしさん・喜津子さんの自宅はある。喜津子さんは五條本町の出身。二人の子どもを育てながら、市の英語教師として働いた後、「イトオテルミー療法」に出会い、広く普及に努めてきた。

一方のたかしさんは旧牧野村の出身。兼業農家の家に生まれ、幼い頃から牛がそばにいる生活の中で育ったという。初めてたかしさんの実家を訪れた時も、「家の中に牛がいて驚いた」と、喜津子さんは笑う。

そらびっくりしました(笑)。でも川村は言うてました。『母親が田植えをしながらいろんなことを教えてくれた』と。俳優の倍賞美津子さんは、『川村先生の作品は土の下の虫や、いろんなものを描いているから好き』と言うてくれていました。ある日、私が庭の草をひいとったら、『草ひきすぎたらコオロギの住むとこなくなるわな』って言うんです。農家で育ったからか、あの人はそんな風に、世界を部分的に見るんでなくて、つながる全体として見ていたようなところがありましたね。
たかしさんは、奈良学芸大学を卒業後、小・中・高校、定時制高校、大学、大学院と順を追って教員を務めた。そのため教え子も多く、夏と正月にはたくさんの学生たちが訪ねてきた。「女の子は振袖を着てきたり、賑やかだった」と、喜津子さんは当時を振り返る。
小説を書き始めたのは1958年頃のこと。子どもに読ませる本がなかったことが、執筆のきっかけだった。たかしさんは次々と作品を書き上げ出版社に持ち込むが、陽の目を見る日はなかなかやってこなかった。書き続けて10年目の1968年、実業之日本社から『川にたつ城』を出版。ダムによって消えていく村を描いた。このデビューを皮切りに、書き溜めた作品を次々と発表していく。
そして、さらに約10年後の1977年に偕成社から出版した『山へいく牛』で、「国際アンデルセン賞優良作品賞」「野間児童文芸賞」を受賞した。『新十津川物語』を執筆中のことだった。

半生をかけて紡いだ十津川との縁
たかしさんの取材は独特だった。“取材”と称さず、小説家と明かさず、ふらっと誰かを訪ね、ほとんど物を言わずに、ただ相手の話に耳を傾けた。“取材”と言ってしまえば、普通に日々を過ごしている人たちは構えてしまい、ありのままの言葉が表れてこなくなるからだ。新十津川町に入った一年目も、そのやり方は変わらなかった。住民から警戒の目で見られたというのも無理はない。
二年目は町役場を訪ねた。当時の町長は富山出身だったものの、副町長が十津川村に縁のある人だったため、協力的に動いてくれたという。木造の役場の一室で、住民に説明する機会が設けられた。集まった年配者の中に、実際に11歳で災害と移住と開拓を経験した94歳の後木喜三郎さんがいた。実体験者の話を聞けたことは何よりの幸運だった。後木さんはこの年に亡くなった。
たかしさんは徹底的に取材する人だった。とにかく歩き回るため、足のマメが潰れ、靴底に血がにじんでいることも度々あった。それを見た喜津子さんは、「絶対に不満を言ったらあかんな」と思ったという。「並大抵ではないんです。取材は…」と喜津子さんは静かに言った。

新十津川物語の第1巻『北へ行く旅人たち』が出版されたのは1977年の12月のことである。
たかしさんが紀伊半島に着目し、「十津川村から新十津川町に移住した開拓民たちの物語を書こう」と決めたのが1972年。構想を描くまでにも取材が必要であるから、構想・取材・執筆に5年以上の年月を費やしたことになる。そして最終巻となる第10巻『マンサクの花』が出版されたのが1988年。1991年から1992年にかけては、NHKが放送した全6回のテレビドラマにもなった。
それ以降も、新十津川町内に、教え子たちの合宿所となる家屋を建てて、度々ゼミ生たちと訪れた。建物は「ライティングハウス」と呼ばれた。40歳で始まった十津川との縁は、たかしさんが80歳で亡くなるまで続いた。
人間を、自然の大きさを、描きたかった
朝、自宅で目を覚まし、朝食をとった後、たかしさんは「行ってきます」と言って家を出た。執筆するために、自宅の隣の書斎棟に向かったのだ。午前中いっぱい執筆すると、12時前には帰ってきて、昼食をとる。また書斎棟へ出かけて行き、17時には帰ってきて、テレビの野球放送を見ながら一杯やる。執筆期間のいつもの風景だった。
そんなある日、たかしさんがぼそっと「あのなぁ、これ書いとったら難儀やわ」と言ったという。「なんで?」と喜津子さんが聞くと、「勝手に人物が動くねん。俺はこっちや言うのに、引っ張られていってしまうねん。難儀やわ」と、ぼやいたと言うのだ。
たかしさんの頭の中には、きっと現実と見紛うような『新十津川物語』の世界が、現実と別に存在していて、たかしさん自身もその世界の住人となって、フキや、そこに生きる人々を見つめていたのではないだろうか。本編中に、登場人物が幾度となく猛吹雪にあう場面が出てくる。
「みんな、先生は吹雪にあったことがないのによう書いたなと笑うんですが、いっぱい資料を読んで、頭の中で練るんでしょうな」と喜津子さんは言う。きっとそうだろう。たかしさんはその世界で、猛吹雪を本当に体験しているに違いない。

だからこそ半端が許せなかったのかもしれない。書き上げた第9巻の原稿に納得がいかず、270枚もの用紙を全て捨てて書き直したことがあったという。そうまでして伝えたかったこととはなんだったのか。
人間を描きたかったんと違いますか。それと、自然の怖さというか、自然の大きさを描きたかったんだと思います。でもね、あの人は本当に私には何も言わない人やったから、私はよう知りまへんねん(笑)。
そう冗談を言って喜津子さんは笑う。しかし、周囲では、フキと喜津子さんのキャラクターがよく似ていると、もっぱらの評判である。たかしさんはもしかしたら、現実では照れ臭くて話せないことを、物語の中にいる奥さんに、たくさん話していたのかもしれない。
Writer|執筆者


合同会社imato代表。編集者/ライター。1981年、熊本県生まれ。神奈川県藤沢市で育ち、2012年に奈良県に移住。宇陀市在住。2児2猫1犬の父。今とつながる編集・執筆に取り組んでいる。