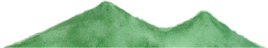亡き父の故郷を思う山添村で、たくさんぶつかって、泣いて、大好きな人たちへの「モチツ」を増やしていきたい。
写真・文・イラスト=井久保詩子(KOEYA) トップ写真=エクストライズ
いろいろあった山添村での7年
夫のUターンに伴い、山添村にやって来てもうすぐ7年が経つ。

今年の3月で36歳になる私は、5歳の長女と2歳の長男、夫、その両親と弟、祖母という8人で暮らしている。
子どもの頃からの「童話作家になりたい」という夢をほんのり抱いたまま、長女が1歳の頃からなぜだか地域おこしのプロジェクトに首を突っ込み、「地域のことを住んでいる人が意外と知らない」「自分で責任を持つ活動がないとあかん」という「そもそも論」にぶつかった結果、長男が1歳になったばかりのときに、無謀にも未経験でフリーペーパー「やまぞえ便利帳」の発行を始めた。

それから1年強が過ぎ、気がつけば「山添村観光協会」のSNSの投稿を担当させてもらい、昨年秋には、「山添村お土産開発部会」として勉強するつもりで参加したイベント「奈良県の宝物グランプリ」においてまさかのスイーツ部門グランプリを受賞。

写真:奈良県奥大和移住・交流推進室
フリーペーパーは月刊を謳いつつ、手が回らない月もあったりで不定期になってしまっているけれど、これまでに13号まで発行。「読んでるわ!」と言ってくれる人がいる限り、まだまだ続けていくつもりでいる。
そんないろんな経験をさせてもらっている山添村は、人口3000人台の村。半数以上が高齢世代で、村内には駅がなく、村外へ行くバスの路線も限られている。
以前は最寄駅から京都駅まで20分とかからない、滋賀県のそこそこ便利な街で暮らしていたので、そちらの知人からは「いわゆる限界集落?」などと言われることもあるけれど、実はそうでもなかったりする。西には奈良市が、東には三重県の伊賀市や名張市があり、スーパーも病院も車で15分とかからず行けるところにある。車にさえ乗れれば、割と難易度の低い田舎だと思う。

画像提供:山添村観光協会
村には20代が少ない。出生数が少ないのはもちろん、ほとんどの子どもたちが、大学進学や就職を機に村外へ出ていくからだ。一方で、ここで何か新しいことや地域おこしなるものをやろうとしているUターン組や移住者の30〜40代は、割と多い。

それはなぜだろう。「都市を知っていると田舎の魅力に気が付きやすい」という面もあるだろうけど、それだけじゃない気がする。こういう人たちは、「自分でここに来たから、その気になれば出ていくこともできる」という人。それでも「ここにいたい」と思うから、やたらがんばって、コミュニケーションをとって、自分がここにいる意味を言語化しようとする、のではないだろうか。
実は私もその一人。
夫のUターンについてきて義両親と同居している「嫁」という立場なので、「渋々来たんでしょ?」と誤解されることも多いが、そうじゃない。私はこの場所にいたい。
田舎暮らしへの憧れと現実
高校生のときに亡くなった実父の故郷は高知県の山奥の町。かつては林業で栄えたそうだが、私が小学生の頃には地理の教科書で過疎化の例に使われるくらい、人口減少が著しい田舎だった。
だけど水が本当に綺麗で、野菜がみずみずしくて、夜と朝が静かで、木の香りがして、星が美しかった。幼い頃から騒がしいところが苦手な性格だった私には、思い切り深呼吸ができる大好きな場所だった。父も祖母も亡くなり、訪ねる機会を失ってからも、その町はテーマパークよりもきらめく思い出として、いつも胸の内にあった。
縁あって夫と出会い、初めて山添村で泊まった夜、静寂と星空に私は一人で感激していた。父の故郷のような清流は「昔のこと」になってしまったそうだが、それでも川が近くにあって、水の音が心地よかった。

「別に珍しくもない」という顔をしている彼が心底羨ましかった。当時は一緒に街中で生活していてUターンの予定も全くなかったけれど、帰省について行くのが、とても楽しみだった。
それから数年、いろいろあって夫がUターンを決め、山添村での暮らしが始まった。
「田舎暮らし」とは言っても、畑はおばあちゃんが家で食べる分を作ってくれているだけで、家はオール電化、トイレも水洗でウォシュレット付き。ネット環境も問題なし。家は広い道路に面しているから車で出かけるのも楽々。田舎の家の名残は残しつつも、家の中はリフォームされて段差の少ないバリアフリー仕様。はじめのうちは、「むしろもっと不便な方がおもしろそうなのにな」と思ったくらいだった。
ところが、毎日の暮らしとなると、やっぱりいろいろ戸惑うことも多かった。
携帯は微妙につながりにくく、一番マシな通信会社を選んで乗り換えなければいけなかった。田舎は静かだといっても、夏になると毎日どこかで草刈機が唸っている。そうしないと草がボウボウになって、大変なことになるからだ。
出前なんか来てくれないし、タクシーも迎えに来てもらうだけで数千円かかる。夫婦喧嘩をして家を飛び出しても、うっかり車のキーを忘れるとどこへも行けない…。数日泊まるならパラダイスだが、暮らすとなると訳が違った。街と比べると、やっぱり田舎は大変だ。
だけど、それでも、ここにいる私は昔よりずっと幸せだと思う。
子どもが夜泣きしたときは外に出て、知っている星座を探しながら声をかける内に気持ちが落ち着いた。ベビーカーで散歩に行くと、帰りにはご近所さんから分けてもらったツヤツヤのエンドウ豆なんかがベビーカーにぶら下がった。
洗濯物が乾かない長雨の日も、家の裏でサワガニがミミズを取り合って綱引きしているのを目撃し、親子で大騒ぎしていたりする。不便な分、そういう小さな幸せが、いちいち愛おしい。
そうして暮らすうちに、だんだんと「私が生きていけるのは、私を生かしてくれる人がいるからだ」と思うようになった。道が平らなのも、電話がつながるのも、当たり前じゃない。どんな住まいでも、そこに人が住めるようにしてくれた人、住み続けられるようにしてくれている人がいる。一人でなんか生きていけない。いつも、どんな一瞬でも、私は誰かに生かされている。
そのことを教えてくれる最たる存在が、子どもたちだ。

20代までの私は、自分のことばかり考えて、人生を悲観しては泣いて、泣き虫な自分がまた情けなくて、失敗して恥をかくたびに、入れる穴を探すような人間だった。
でも今は、私のことを毎日「ママ大好き!」と言ってくれる子どもがいる。こんな幸せなことがあるのかなと思う。髪がボサボサでも、オナラをしても、「ママ大好き!」と言ってくれる。子どもは「存在を無条件で肯定する」という最大級の対価をくれる、最高のお得意様だ。
おまけに24時間危なっかしくて、しょっちゅう死の恐怖を味あわせてくれるから、入る穴を探す暇がなくなった。
生活の中で思い出した「モチツモタレツ」
「モチツモタレツ」という言葉に触れたのは、小学生のときに読んだ角野栄子さんの『魔女の宅急便2」が最初だったと思う。
どういう場面で使われていたのかは忘れてしまったが、確かカタカナで書いてあった。「マハリクマハリタ」みたいで、呪文っぽくて、かわいいなと思ったような記憶がある。そこから私は、「誰かの役に立つこと、誰かの助けになることが『仕事』なんだよ」というメッセージを受け取った。
以前販売の仕事をしているときに、上司に「送料ってね、かかるのが当たり前なのよ。取引先と運ぶ人を大事にしなさい」と言われたことがあった。当時はその言葉の意味についてあまり掘り下げて考えられなかったけれど、車必須の生活になった今、「運んでもらえることのありがたさ」をひしひしと感じる。
長女の妊娠中から長男が産まれるまで、私の移動手段は徒歩か、誰かに乗せてもらうか、家族の車を借りて近場へ行くしかなかった。身重や子連れでは、徒歩で行けるところなんて知れている。車に乗せてもらうにも、借りるにも、いちいちお願いしないといけない。インドアは好きだけれど、たまには外に行きたい。誰かと話をしたい。そんな中、通販すれば必要なものが届くのは本当にありがたかった。
「持ちつ持たれつ」という言葉を調べると、類義語として「ギブアンドテイク」が挙げられる。
確かに似たような言葉だけど、なんだかそれだと、対面している感じで私にはいまいちしっくりこない。「持ちつ持たれつ」と言うと、一緒に同じ目的地に向かって歩いてる感じがする。例えば、足を引きずる人に肩を貸していて、でも実は、その人の温もりに助けられて雪山を二人で越えているような。
いつしか私は、そんな「モチツモタレツ」という言葉を思い出し、それを大切に生きていきたいと思うようになった。

そして、この「モチツモタレツ」を思い出したとき、村での暮らしで幸せを感じているのに、いつもモヤモヤしている自分がいることに気が付いた。この村で、私にとって「モタレツ」の機会はたくさんあるけれど、「モチツ」の機会がなかったのだ。
どこでも通用するような資格もなければ、日がな一日畑に出てイチから農業を勉強する体力もない。義父母はそれなりに忙しくて、毎日子どもを預けて働きに行くわけにもいかない。専業主婦であることを責める人は誰もいなかったし、子どもが保育園に入る年齢まで、家を綺麗にして料理をしていればそれでいいはずだった。
イラストが好きなのだから、「SNSで田舎暮らしエッセイ漫画でも描いていれば周りともつながれるじゃないか…」とも思った。けれど、もっと直接的な生身のつながりに、やたらと飢えていた。公民館活動に行ってみたり、パパに娘を任せられる休日だけアルバイトしてみたりして、モヤモヤからは少し解放された。
それでも、子どもが熱を出すとやっぱり思うようには働けない。「在宅での仕事を勉強しようか…」と思っていた頃、育児サークルでお世話になっている栄養士さんが関わる「山添村お土産開発部会」に出会う。
村の代表的な観光施設のひとつ「めえめえ牧場」のイベントに出店されていて、部会メンバーには育児中のママもいた。まさに開発中という「大和茶のジャム」も、本当においしかった。そして思わず、「私も参加することって、できますか?」と食いついたのだった。

部会に入ってから、少しかじったことのあるグラフィックデザインやイラストを使ってチラシを作ったり、商品のラベルを作ったり、なんとか「モチツ」できるようになりたいと取り組み、みんなで完成させた初めての商品には、期待の声もたくさんいただいた。けれど、製造体制などうまくいかないことが重なり、一時はせっかくの商品がお蔵入り状態になったりもした。
「自分たちにできることだけでは、何ごとも続けていけない」
「もっと、いろんな人に助けてもらえるネットワークを持たなければいけない」
「そのためには、自分がもっと村を知り、村の人に会わなければいけない」
そんな考えに行き着いたとき、ご縁があって「村民向けフリーペーパー」の制作者という顔を持つことができ、取材という名目で、いろんな人に会いに行き始めた。役場から紹介していただいた「奈良県よろず支援拠点」にも、頻繁に相談させていただいている。
取材やチラシを置いてもらうお願いを通じてたくさんの新しい知り合いができて、地域おこしのプロジェクトやセミナーに声をかけてもらうことも多くなった。その中で「奈良県の宝物グランプリ」に出会い、部会メンバーに「なんとか挑戦してみたい。一緒にやってくれますか」と声をかけた。
レシピを作ったのは私じゃないけれど、みんなで作り上げた商品には誇りをもっている。「たとえ評価されなくても学びを次に繋げていくんだ」と勇気を振り絞ってプレゼンに立った。
その挑戦の結果が、スイーツ部門でグランプリだなんて、想像もしていなかった。今、迫る全国大会に向けて、たくさんの人に助けてもらいながら、準備に駆け回っている。

私の「モチツ」はまだ始まったばかりで、これからも何度も壁にぶつかるんだと思う。苦手なことが得意にはならないし、相変わらずプロを名乗れる資格もない。でも、たくさんの「モタレツ」に、毎日感謝が溢れて泣くくらいうれしい。というか、泣いている。同じくらい情けなさで泣くことも相変わらず。でも、泣き虫な自分がそれほど嫌いじゃなくなった。
村に来る前、泣いてばかりだった私にも、助けてくれる人はいた。その人たちに「申し訳ない」とばかり思っていたけれど、今はそれ以上に「ありがとう」を伝えたい。いっぱいぶつかって、いっぱい「助けて!」と叫んで、泣きまくりながら「モチツ」を増やしていきたい。
「魔女の宅急便」でキキを助けてくれた大人たちみたいに、10年後、20年後、これまでの私のように苦しむ若者に、「モチツモタレツで行こう!」と、ドーンと胸を叩いて言ってあげられる大人でありたい。子どもが大きくなって、自分の夢のために村から羽ばたきたくなったとき、「行っておいで、疲れたらいつでも帰っておいで」と言える親になっていたい。
大好きなみなさま、これからも、益々よろしくお願いいたします。

Writer|執筆者


滋賀県大津市育ち。2児の母。夫のUターンに伴い、2016年より山添村民になる。「KOEYA-こえや-」の屋号で、フリーペーパー「やまぞえ便利帳」を制作・配布するなど、人々のつなぎ役となるべく活動中。