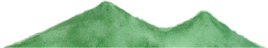奇跡みたいな風景は、住んでいる人たちの声に応え続けて生まれた。吉野町国栖にある「くにす食堂」と、店主・糟谷陽一さんのお話。
ある一日の、食堂の風景
雄大な吉野川を望む駐車場に車を停め、道路の向かい側に目線を送ると、そこには集落の風景によくなじむ、美しい佇まいの古民家が建っている。
ガラガラガラ、ガラ。
大きなガラス戸を開けて、中へ。

どっしりとした木造りのカウンター。壁一面の棚には、フィルムカメラや珈琲豆、雑貨類が並べられ、最近はあまり見ることもなくなったコーヒーチケットが、びっしりと、綺麗に整列して貼られている。暖色の光の照明がやさしい。
目に映るどこか懐かしさを感じる風景に見惚れていると、「いらっしゃいませ」と声がして、奥からニット帽をかぶった男性が満面の笑顔で出迎えてくれた。

ここ「くにす食堂」は、春の桜で有名な吉野山、良質な木材(通称・吉野材)が集まる貯木場などで知られる吉野町の東端、人口900人ほどの国栖(くず)という地域に、2年ほど前にオープンした。ニット帽の男性は店主の糟谷陽一さん、その人だ。
糟谷さんに促され、靴を脱いで店内へ。
左手の窓側の2人席には20代と思われる若い男女が座り、奥の4人席では40~50代くらいの女性たちが楽しそうに食事をしている。右斜前のテーブル席には、60代くらいと思われるやや年配の男女3人のグループ。僕と友人は、2つある右手の座卓席に通され、小さな子連れのご家族の奥、中庭が見える窓側の席に腰を下ろした。

薄くゆっくりと流れる、ピアノと電子音が奏でるBGM。あちこちに置かれた灯油ストーブの火が、静かに揺れている。
やがて糟谷さんが注文を取りにきてくれる。僕と友人の分、ランチを2つ注文する。

鶏もも肉の卵とじ。ほうれん草としめじのおひたし。自家製肉みそ豆腐。お漬けもの。お味噌汁。ごはん。見ての通り、どれも素朴。だけど、不思議とここでしか食べられない味。作っているのは近所に住むお母さんたちだ。
食後にコーヒーを注文。店内で豆を焙煎し、糟谷さんが一杯ずつ淹れてくれるコーヒーも、言わずもがな、おいしい。
友人に自家製プリンを勧めたら、彼は「たまには妻のご機嫌もとっておかないとね」と家族分をお土産に買っていった。どこか昭和のお父さんみたいな物言いだったけど、何かの映画のワンシーンみたいだった。ふと物語の中にいるような、そんなふうに思いたくなる雰囲気が、このお店にはある。
「何も知らない世界」を求めて
糟谷さんは、今年30歳。
愛知県の知多半島にある、人口5万人ほどの街の出身だ。
本人は、「勉強は好きだったけど、できなかった」と笑う。大学で建築を学ぶも、「人と違うことがしたい」という思いが強く、いわゆる就職活動に取り組むことはなかったそう。それでも、当時のゼミの先生からの後押しを受けて、マンションの施工管理などを請け負う大手ゼネコンに勤務することになる。
やりがいはあったものの、毎日が同じようなことの繰り返し。現場を通じて100~200の人を相手にするうちに、だんだんと心がやさぐれていくのを感じる。常に「これでいいんだろうか…」という思いを抱えたまま、それでも2年半が過ぎた頃、糟谷さんは60歳くらいのある上司と出会う。
たくさんの人が関われば、それだけ意見のベクトルが増えていく。その矢印をうまく受け止め、時に流し、紐解いたり、束ねたりしながら、実に巧みに、みんなが収まるひとつの方向へ流していく。糟谷さんは上司のその手腕に驚き、魅了される。そして、2人で話す機会があった際、糟谷さんは思わず故郷について尋ねたという。それが、糟谷さんと「吉野町」の出会い。

職場の上司の故郷というだけの、見たことも聞いたこともない町。調べてみたら、知っているお店は「ローソン」しかなかった。
「何も知らない世界」がある。
糟谷さんはそのことに衝撃を受ける。育った街は、時代による効率化・平均化の波を受け、どこに行っても同じような風景が広がる。でも、ここには、知っているものはたったひとつのコンビニしかない。
「住みたい!」という言葉が口をついた時には、会社を辞める気持ちが固まっていた。吉野町で何をしたいわけじゃない。町に対して、夢や希望を抱いたわけでもない。とにかく、環境を変えたかった。住んでみたい、暮らしてみたい。それだけだった。
住むのであれば、何か仕事を見つけなければならない。早速、「吉野町 アルバイト」で検索してみると、ハローワークのページに「地域おこし協力隊 募集」の文字が映し出された。月16日の勤務日数。仕事内容は、国栖地区自治協議会のサポートと、あとは地域のためになることを見つけて取り組んでください、というようなことが書いてある。
糟谷さん:これだと思いました。昔から人と違うことがかっこいいと思う方で、でも、何をすればいいのかはずっとわからなくて。学生時代はとにかくモテたくて、サッカーに打ち込んだり、仲間とバンドを組んでオリジナルの楽曲でライブをしたりもして。
でも、自分の能力の限界は、なんとなく感じていて、名古屋や東京にいたら、「よくいる人」になってしまうかもしれない。そんな怖さに怯えていたんだと思います。吉野だったら、街で輝くことができなかった自分も、もしかしたら…。今思えば、そんな思いがあったのかもしれないですね。
糟谷さんは5年前を振り返り、笑う。
そして2016年11月。
24歳の秋。単身、吉野町での暮らしが始まった。
声を頼りに手探りした、協力隊としての3年間
地域おこし協力隊としての1年目。役場の方の取り計らいで、国栖地区に空き家を見つけ、無事に住むことができた糟谷さんは、「まずは基盤をつくろう」と考える。そのためには何より、住んでいる人たちに自分を知ってもらわなければならない。チラシをつくり、全世帯に配って、とにかく毎日誰かに会いに行った。
2年目は、「孫の手プロジェクト」と銘打ち、「地域の困りごとを何でも解決する」という取り組みをスタート。地域を歩き、「困ったことがあったら何でもいいから電話してください」と、また全世帯に伝えて回った。すると、畑の手伝い、パソコンの使い方、年賀状の作り方、そのほか力仕事など、さまざまな相談が舞い込むようになる。経験がないことも、手探りでチャレンジ。やっているうちにできるようになった。

ちなみに田舎は、無料の頼みごとを苦手とする人が多い。手伝いを終えた帰り道、両手には必ずと言っていいほど野菜やビール、いろんなお土産が握られていた。
地域の人たちが求めていることをしたい。
改めて思った糟谷さんは、住民の皆さんにアンケートを取ってみる。すると、「気軽に集まれる場所がほしい」という声がたくさん聞かれた。
じゃあ、どうしたらみんなが楽しく集まれるだろう?
糟谷さんは考え、「みんなが参加できるマルシェをしよう」と思い立つ。野菜を育てるのが上手な人、パンやごはん、お惣菜を作るのが好きな人、手芸品を作っている人、ケーキが作れる人。心当たりに声をかけていくと、みんな快諾してくれた。企画を知って、運営の手伝いを申し出てくれる人も現れた。コーヒーが好きだった糟谷さん自身も、キャラメルカプチーノを販売することに決めた。
そして、開催日当日。「くにす食堂」になる前の古民家にはたくさんの人がやってきた。みんな、国栖の人たちだ。手作りの小さなマルシェは、大成功だった。

3年目。マルシェの参加者から集めたアンケートに、今度は「ごはんを食べられる場所があったらうれしい」という声がたくさん寄せられていた。
料理なんてできないけど、やってみたい。
糟谷さんの頭に、3人のお母さんの顔が浮かぶ。7年前から月に1回お弁当を作って、地域に向けて販売していたメンバーだ。相談に行くと、快諾の返事と一緒に、「それやったら社協(社会福祉協議会)の力も借りたらええよ」と助言をもらい、そのおかげで、吉野町社会福祉協議会の協力も得ながら、食堂を開くことになった。
食堂の名前は話し合いの末、国栖小学校跡地の廃校活用プロジェクトで採用されていた「くにすの杜」にあやかって、「くにす食堂」に。このとき、「くにす」は、日本最古の書物である『古事記』や古代の歌集『万葉集』に登場する「国栖」の読み方だと知った。
そして2019年3月6日。手探りの「くにす食堂」オープン当日は、糟谷さん本人の言葉をそのまま借りれば、「どえらい数の人」がやってきた。60食用意したランチは、瞬く間に完売した。
まさか、こんなに来てくれるなんて。
料理を作ってくれたお母さんたちと、顔を見合わせた。そのときのお母さんたちは、とてもうれしそうな表情をしていた。奇跡みたいだと思った。
近所に食堂ができるなんて、何十年ぶりだろう。うれしいなぁ。
そんな声をたくさんいただく。こんな風景をいつも見ていたい。イベントではなく、毎週やりたい。もう迷いはなかった。糟谷さんは役場の担当者と相談し、準備を進めていった。
地域おこし協力隊の任期は3年。最後の3ヶ月は、週に1日オープンした。たくさんの人がやってきて、笑って、食べて、「ありがとう」と言って帰っていく。そこには毎回、やさしい、奇跡のような風景が広がった。お客さんにも、スタッフのお母さんたちにも、ずっと助けてくれる役場の方にも、感謝しかなかった。
そんなころ、「くにす食堂」を語る上で欠かせないもうひとつの出来事があった。お店のアートワークを担う、デザイナーのナツマヤさんとの出会いだ。

ナツマヤさんは当時、神奈川県から上市に移住してきたばかりで、役場の方が引き合わせてくれた。ロゴからショップカード、スタンプカード、メニュー、自家焙煎コーヒーのパッケージ、コーヒーチケット、チラシ、オンラインショップ、オリジナルグッズなど、店に関するデザインを担当。国栖で「うちゅうねこ」という名前でアトリエ兼ギャラリーを開いている。
オープン、休業、そしてこれから
協力隊の任期を終了後、1ヶ月のお休みを経て、2019年11月に「くにす食堂」はグランドオープンを迎える。毎週金土日の3日間、元薬屋だった古民家に明かりが灯るようになった。

当初は空席がある日もあったものの、お店の雰囲気、おいしいごはんとコーヒー、比較的リーズナブルな価格、その評判が広まるのには、さほど時間はかからなかった。
半年ほど経ったころ、ランチが予約でいっぱいになる日が続くようになる。そうして軌道に乗り始めたと思った矢先、新型コロナウイルスの感染拡大が報じられ始め、「くにす食堂」も休業を余儀なくされる。でも、糟谷さんはポジティブだった。オンラインショップの開設、珈琲豆焙煎機の導入、その他オリジナルグッズの企画・開発。この期間を、「今しかできないこと」へのチャレンジに充てた。
半年間の休業を経て、2020年10月にお店を再開。不安はあったものの、蓋を開けてみたら、不思議と休業前よりもお客さんは増えていた。以降、ランチが予約で埋まらない日は稀だという。
そういう店の状況をスタッフのお母さんたちが喜ぶ姿を見るのが、自身の喜びでもあると糟谷さんは言う。

糟谷さん:お客さんがいっぱいきてくれて、席が埋まって、ランチが完売して。そのことを、お母さんたちが自分のことのように喜んでくれる。以前、テレビの取材が来て、お母さんたちがテレビに映って、みんな親戚や友達からすごいねって言われたらしくて。それを僕に本当にうれしそうに話してくれる。そういうことが本当にうれしい。
今、僕がこんなことができているのは、間違いなく、地域の皆さんの無償の愛のおかげです。お店をしているとか関係なく、僕が存在していることを喜んでくれて。だからこそ、僕も恩を返したい。もらった以上のことで返したい。少しでも長く、この場所にいたい。いることで、安心して、喜んでくれる。そういう関係が、うれしいです。
オープンから2年が経ち、いよいよ経営も軌道に乗ってきた今、糟谷さんは「古道具屋を始めたい」と次の目標を教えてくれた。
糟谷さん:お店をしていると、ご近所で昔の家具や道具を捨てているのを目にしたり、聞いたりすることが多くて。うちのお店を好きな人は「古いもの好き」な人が多いので、捨てられてしまっている古道具と、それを欲しい人をつなぐことができたらいいなと思ってます。
その先のことは、あんまり考えていなくて。速過ぎても、落としちゃうから、これからも目の前のことを大切にしながら、ひとつひとつやっていこうと思います。ありがとうございました。
お店を訪ねるたび、糟谷さんは掌を合わせ、「ありがとう」と何度も言ってくれる。その言霊は僕の心に作用して、自然と「ありがとう」が口をついて出る。きっと、そんなやりとりが、毎日お客さん、スタッフのあいだで交わされているんだろうと思う。ささやかな「ありがとう」が始まる、でも奇跡のようなお店が、この吉野の地にありました。

Writer|執筆者


合同会社imato代表。編集者/ライター。1981年、熊本県生まれ。神奈川県藤沢市で育ち、2012年に奈良県に移住。宇陀市在住。2児2猫1犬の父。今とつながる編集・執筆に取り組んでいる。